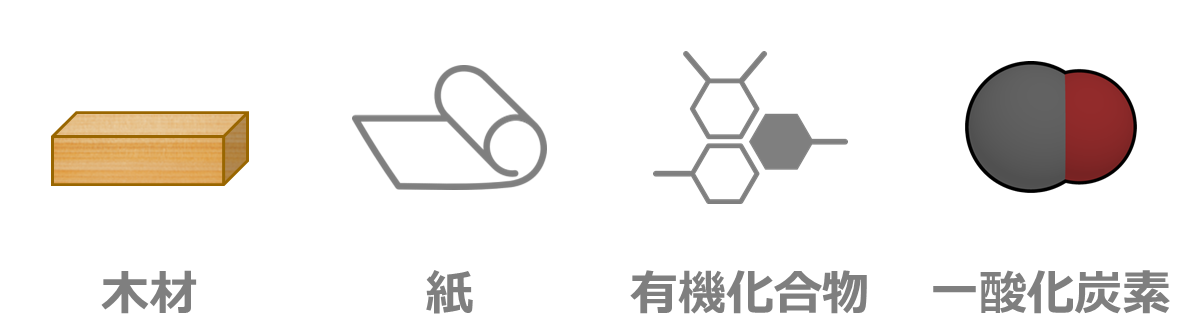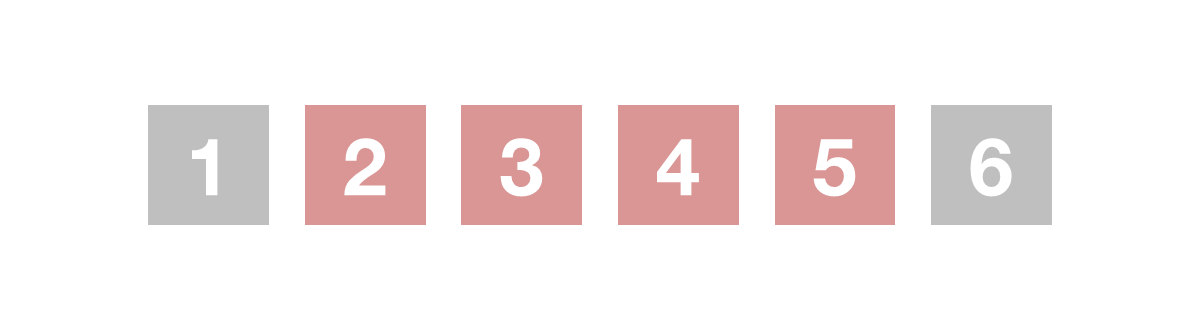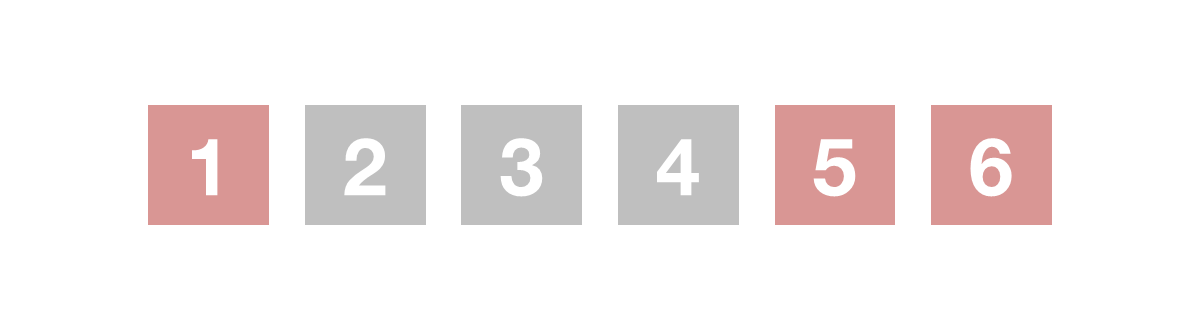燃焼の3要素 - モノを燃やすのに必要な3つの要素

このページでは、燃焼理論について学びます。
まずは、「火」や「炎」といった日常でもよく使う「燃焼」に関する用語の意味を確認していきます。
その上で、燃焼に必要な3つの要素について見ていきましょう。
スポンサーリンク
燃焼
燃焼(ねんしょう)とは、熱と光の発生を伴う酸化反応のことです。
酸化反応については下の記事を参考にしてください。
火や炎といった日常的に何気なく使用している言葉についても参考のためご紹介します。
火
熱と光を出す現象のことを火(ひ)といいます。
炎
気体の燃焼による激しい火のことを炎(ほのお)または火炎(かえん)といいます。
有炎燃焼
炎の有る燃焼のことを有炎燃焼(ゆうえんねんしょう)といいます。
無炎燃焼
炎の無い燃焼のことを無炎燃焼(むえんねんしょう)といいます。燻焼(くんしょう)や表面燃焼(ひょうめんねんしょう)ともいいます。例としては線香やタバコの火が挙げられます。
爆発
急激な熱エネルギーの放出によって、気体の温度と圧力が上昇することで起こる爆音を伴う燃焼のことを爆発(ばくはつ)といいます。
燃焼を起こすには、3つの要素が必要になります。その要素とは何かを確認していきましょう。
スポンサーリンク
燃焼の3要素
燃焼に必要な3つの要素である可燃物、酸素供給体、点火源を「燃焼の3要素」といいます。
この3要素のどれか1つでも欠ければ、燃焼は起こりません。
逆に、消火したい場合は3要素の1つでも除去できればよいということになります。
それぞれの要素について、詳しく見ていきましょう。
可燃物(可燃性物質)
可燃物(かねんぶつ)とは、燃える物のことです。可燃性物質(かねんせいぶっしつ)ともいいます。
例としては、木材、紙、多くの有機化合物、一酸化炭素等があります。
危険物の中では、第2類危険物、第3類危険物、第4類危険物、第5類危険物が該当します。
酸素供給体(支燃物)
酸素供給体(さんそきょうきゅうたい)とは、酸素の供給源となる燃焼を助ける物質のことです。
燃焼を支える性質を持つため、支燃物(しねんぶつ)ともいいます。
空気中の酸素のみにあらず
空気中の酸素のほか、酸化剤中の酸素(第1類危険物、第6類危険物)や可燃物中の酸素(第5類危険物)も酸素の供給源になります。
酸素供給体は、空気中の酸素のみではないことに注意しましょう。
また、酸素があれば必ず燃焼を起こすわけではありません。
必要な酸素濃度が存在します。
限界酸素濃度
限界酸素濃度(げんかいさんそのうど)とは、可燃物の燃焼に必要な酸素濃度のことをいいます。
可燃物の種類によって異なる値を示します。
点火源
点火源(てんかげん)とは、可燃物と酸素との反応を起こさせるエネルギーのことです。熱源(ねつげん)や点火エネルギー、熱エネルギーともいいます。燃焼のきっかけとなります。
火気、火花、静電気、摩擦熱等が該当します。
燃焼の4要素
最後に「燃焼の4要素」についても触れておきます。
燃焼の継続
燃焼が継続していくためには連続した酸化反応が必要です。
酸化の連鎖反応のことを燃焼の継続(ねんしょうのけいぞく)といいます。
燃焼の3要素に、燃焼の継続を加えて「燃焼の4要素」と呼ぶことがあります。
スポンサーリンク